2025年12月号
「第9回:絵具と釉薬」
あっという間に今年も残すところ僅かとなりました。開催中の『古伊万里カラーパレット―絵具編―』(~12月21日(日))も会期末が迫っております。今年の夏秋の展覧会は連続企画として伊万里焼の色による装飾をご紹介してきました。じつは夏展で特集した釉薬(ゆうやく)は絵具の発色にも密接に関わっています。
釉薬とは、やきものの表面に施されるガラス質の膜のことを言います。釉薬をやきものに施すことで、機能面では耐久性や耐水性を付与することができ、装飾面ではつやや色彩をもたらします。江戸時代の伊万里焼に使用される主な釉薬は透明釉のほか、瑠璃釉、青磁釉、銹釉といった有色の釉薬(色釉)もあります。
伊万里焼の絵付け技法は下絵付けと上絵付けの2つに大別されます。前者は「釉下彩」とも言い、字の如く釉薬の下に絵付けを施す技法、後者は「釉上彩」、釉薬の上に絵付けを行う技法です。下絵付けの絵具は釉中に絵具が溶け込むことで発色し、上絵付けは絵具を釉面に低温で熔着させて施します。つまり、どの絵付け技法であっても釉薬の存在が重要な役割を果たしています。(図1)。

特に使用されるのは透明釉です。素地の白地を透かすため、筆による施文を装飾の主軸とした伊万里焼に適した釉薬であったのでしょう。なお、色釉と絵付けを併用することも可能ですが、透明釉を掛けた場合とは異なる趣になります(図2)。

ところで釉薬と絵具は呈色剤に着眼すると共通項を見出すことができ、いずれも酸化金属を発色の材料としています。特に下絵付けや色釉の場合は、本焼きの焼成温度である1200~1300度程度の高温に耐えうる酸化金属でないと理想の発色は叶わず、また、適切な温度や焼成状況も異なります。そのため、使用できる酸化金属は限定されます。
例えば、染付は下絵付けの代表的な技法ですが、その呈色剤となるコバルトは高温焼成に耐え、比較的安定して青色を発色できるのが特徴です。これを透明釉に数パーセント混ぜると、同じく青色を呈する瑠璃釉を作ることができます(図3)。

また、作例は少ないですが、下絵付けで赤色をあらわす辰砂の呈色剤である酸化銅も、透明釉に混ぜて辰砂釉として使用されることがあります。ただし、銅はコバルトほど高温に耐えられず、さらに還元炎か酸化炎かといった細かな焼成環境で色調に変化が生じやすいという特徴があります。
当館収蔵の辰砂作品も、絵付け部分の色が沈んでしまったり、還元しきらずに緑がかったり、高温によって絵付け部分の色が揮発して周辺に散るあるいは消えるなど、様々な苦労が垣間見えます。また、辰砂釉も、鮮明な赤と言うよりは紫がかった茶色に発色しています(図4)。辰砂は、伊万里焼では絵具としても釉薬としても安定した発色を得られなかったようで、酸化鉄(ベンガラ)を呈色剤とする上絵の赤の台頭と共に姿を消していきます。

このように、下絵付けと色釉は、釉中に呈色剤が熔けこむという点に共通点が見出せます。絵具と釉薬は一見するとあまり関連性が無いように思えますが、釉薬は絵具にとって重要な基盤となる要素です。また、呈色剤の特性を見出すと、例えば瑠璃釉染付の作品は、絵付けも釉薬も酸化コバルトが発色の材料になっていることに気が付き、ひとつの色彩における表現の幅広さをうかがい知ることができます。
今回の夏秋連続企画展示「古伊万里カラーパレット」を通じて、絵具や釉薬といったやきものを構成する素材や色に関心をお寄せいただけましたら幸いです。
【主な参考文献】
佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方1 種類』同2004
佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方3 装飾』同2006
樋口わかな『やきものの科学』誠文堂新光社2021
釉薬とは、やきものの表面に施されるガラス質の膜のことを言います。釉薬をやきものに施すことで、機能面では耐久性や耐水性を付与することができ、装飾面ではつやや色彩をもたらします。江戸時代の伊万里焼に使用される主な釉薬は透明釉のほか、瑠璃釉、青磁釉、銹釉といった有色の釉薬(色釉)もあります。
伊万里焼の絵付け技法は下絵付けと上絵付けの2つに大別されます。前者は「釉下彩」とも言い、字の如く釉薬の下に絵付けを施す技法、後者は「釉上彩」、釉薬の上に絵付けを行う技法です。下絵付けの絵具は釉中に絵具が溶け込むことで発色し、上絵付けは絵具を釉面に低温で熔着させて施します。つまり、どの絵付け技法であっても釉薬の存在が重要な役割を果たしています。(図1)。

特に使用されるのは透明釉です。素地の白地を透かすため、筆による施文を装飾の主軸とした伊万里焼に適した釉薬であったのでしょう。なお、色釉と絵付けを併用することも可能ですが、透明釉を掛けた場合とは異なる趣になります(図2)。

ところで釉薬と絵具は呈色剤に着眼すると共通項を見出すことができ、いずれも酸化金属を発色の材料としています。特に下絵付けや色釉の場合は、本焼きの焼成温度である1200~1300度程度の高温に耐えうる酸化金属でないと理想の発色は叶わず、また、適切な温度や焼成状況も異なります。そのため、使用できる酸化金属は限定されます。
例えば、染付は下絵付けの代表的な技法ですが、その呈色剤となるコバルトは高温焼成に耐え、比較的安定して青色を発色できるのが特徴です。これを透明釉に数パーセント混ぜると、同じく青色を呈する瑠璃釉を作ることができます(図3)。

また、作例は少ないですが、下絵付けで赤色をあらわす辰砂の呈色剤である酸化銅も、透明釉に混ぜて辰砂釉として使用されることがあります。ただし、銅はコバルトほど高温に耐えられず、さらに還元炎か酸化炎かといった細かな焼成環境で色調に変化が生じやすいという特徴があります。
当館収蔵の辰砂作品も、絵付け部分の色が沈んでしまったり、還元しきらずに緑がかったり、高温によって絵付け部分の色が揮発して周辺に散るあるいは消えるなど、様々な苦労が垣間見えます。また、辰砂釉も、鮮明な赤と言うよりは紫がかった茶色に発色しています(図4)。辰砂は、伊万里焼では絵具としても釉薬としても安定した発色を得られなかったようで、酸化鉄(ベンガラ)を呈色剤とする上絵の赤の台頭と共に姿を消していきます。

このように、下絵付けと色釉は、釉中に呈色剤が熔けこむという点に共通点が見出せます。絵具と釉薬は一見するとあまり関連性が無いように思えますが、釉薬は絵具にとって重要な基盤となる要素です。また、呈色剤の特性を見出すと、例えば瑠璃釉染付の作品は、絵付けも釉薬も酸化コバルトが発色の材料になっていることに気が付き、ひとつの色彩における表現の幅広さをうかがい知ることができます。
今回の夏秋連続企画展示「古伊万里カラーパレット」を通じて、絵具や釉薬といったやきものを構成する素材や色に関心をお寄せいただけましたら幸いです。
(小西)
【主な参考文献】
佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方1 種類』同2004
佐賀県立九州陶磁文化館『古伊万里の見方3 装飾』同2006
樋口わかな『やきものの科学』誠文堂新光社2021
.jpg)

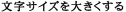



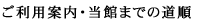

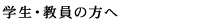
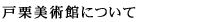
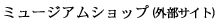
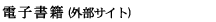


 2025年
2025年





































































































































































































