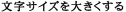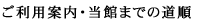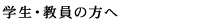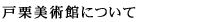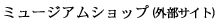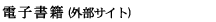17世紀の古伊万里―逸品再発見Ⅰ―展
■会期 2017年5月27日(土)~9月2日(土)■開館時間 10:00~17:00(入館受付は16:30まで)
※毎週金曜は10:00~20:00
(入館受付は19:30まで)
■休館日
月曜
※7月17日(月・祝)は開館、7月18日(火)は休館
※毎月第4月曜はフリートークデーとして開館
 出展作品リスト
出展作品リスト
展覧会概要
「うつわを見る」時、何に注目されるでしょうか。何焼であるのか、何に使うものか、あるいは色や文様でしょうか。しかしこれらの他にも、やきものには実に多くの見所があるのです。同じ「古伊万里」でも、丸い皿もあれば四角い皿、花形の皿もあり、素地の白さも青味がかったものもあれば乳白色のものもあり、一様ではありません。それぞれの違いが何によって生まれているのか、一歩踏み込んで考えながら観察していると、ふと、うつわの新たな一面を発見できることがあります。その時、今まで目に留めることのなかった作品が、急に自分だけの「逸品」になるかもしれません。
とくに今回取り上げる17世紀は古伊万里にとって、誕生と技術革新によって、多様な作品が生み出された時代です。「かたち」や「素地の白」など15のテーマのもとに並んだ個性豊かな約70点を、じっくり観察しながら皆様のお気に入りの「逸品」を是非探してみてください。
主なテーマと鑑賞ポイント
①かたち-成形技法

(左から)染付 花卉幾何文 菊花形鉢、染付 花唐草文 長皿、染付 孔雀形香合 伊万里焼の中で最も多く見られるかたちは丸皿で、轆轤(ろくろ)という回転台を利用して成形します。しかし丸皿以外にも、菊形や長方形、鳥形の伊万里焼も見られます。「染付 花卉幾何文 菊花形鉢」は轆轤で成形した後、土型に被せて叩く「型打ち成形」によって、菊形に変形させたもの。「染付 花唐草文 長皿」は轆轤を使わず、板状に切り出した粘土を土型に押し付けて変形させる、「糸切り成形」によるものです。このほか轆轤を使わない方法として、「型押し成形」もあります。この技法は「染付 孔雀形香合」のように、幾つかのパーツに分けて外型を作っておき、そこに粘土を押し付けて型に沿って変形させた後、個々のパーツを貼り合わせています。このように多様な成形技法を用いることによって、様々なかたちが生み出されました。
②赤と青-下絵付けと上絵付け

「辰砂 草花文 瓶」と「色絵 丸文 瓢形瓶」はどちらも赤色の絵付けが施されていますが、前者はやや褐色に近い発色、後者は明るい発色です。この違いは発色の主成分が前者は銅、後者は鉄であるためですが、それだけではなく、両者は絵付けのタイミングも異なります。前者は釉薬を掛ける前に絵付けをし、後者は釉掛け・本焼き焼成後に絵付けしてもう一度焼いたもの。絵付けの位置が釉薬の下か上かで異なるので、それぞれ下絵付け、上絵付けと呼びます。下絵付けの絵具は本焼き時の1,300度以上の高温に耐えられるものでなければならず、色数は多くありません。赤色は辰砂(しんしゃ)、「染付 岩鳥文 皿」のような青色は呉須(ごす)で表しています。呉須による下絵付けの技法およびその技法によるやきものを染付(そめつけ)と呼びます。伊万里焼の鮮やかな色がどのように表されているのか、絵付けの技法にもご注目ください。
③素地の白-色絵専用素地と染付素地

「色絵 鳳凰花鳥文 十角鉢」と「染付 団龍文 輪花鉢」とでは素地の白さが異なって見えます。前者は1670年代に成立する柿右衛門(かきえもん)様式の特長である濁手(にごしで)素地で、温かみのある乳白色を呈しています。濁手素地は色絵専用の素地で、土そのものの白さを活かし、釉薬はごく薄く掛けてあります。ガラス質である釉薬は厚くなるほど青味がかって見え、上絵の色の見え方に影響が出るためです。一方、後者は染付が用いられていることが特徴ですが、染付は釉薬にある程度の厚みがないと鮮やかに発色しません。染付の美しい発色は少し厚みのある釉薬、その必然としての青味のある素地があればこそ。伊万里焼では絵付けの色がそれぞれ最も美しく見えるよう、素地から作り分けていたのです。
同時開催
第3展示室「磁器生誕から100年の変遷」
伊万里焼の創始期から元禄年間までの100年を年代順にその様式の特徴にそってご紹介いたします。伊万里焼の技術を昇華させ、徳川将軍家への献上を目的に創出された鍋島焼も展示。
特別展示室「九州のやきもの 波佐見焼」
長崎県東彼杵郡波佐見町で江戸時代から焼かれ、約400年の歴史を持つ波佐見焼。今展では波佐見焼のはじまりから現代に至るまでの発展の流れをパネル展示でご紹介しています。
1階やきもの展示室「第3回 望月優作品展 ~今と昔をつなぐ~」
陶片をモチーフに“今と昔をつなぐ”をテーマに器を制作。伝統技法の轆轤、型打ち、上絵、下絵などを使いながらも、今を表現する器、遊び心がある器を展示いたします。
会期中のイベント
展示予定作品の画像データ等ご用意しております。
取材は随時受け付けておりますので、下記の問い合わせ先へご連絡いただき、掲載媒体・取材内容についての企画書をお送りください。内容を検討し、追ってご連絡いたします。
●PDFファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 『17世紀の古伊万里―逸品再発見Ⅰ―展』プレスリリース
『17世紀の古伊万里―逸品再発見Ⅰ―展』プレスリリース 写真借用申請書
写真借用申請書【お問い合せ先:公益財団法人 戸栗美術館】
TEL:03-3465-0070
FAX:03-3467-9813
.jpg)