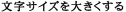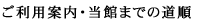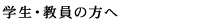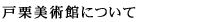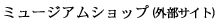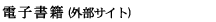戸栗コレクション1984・1985―revival―展
会期:2016年10月4日(火)~12月23日(金・祝)

色絵 牡丹文 瓶
伊万里
江戸時代
(17世紀中期)
高47.0cm

色絵 壽字吉祥文 鉢
伊万里
江戸時代
(17世紀末~18世紀初)
口径22.1cm

青磁染付 雪輪文 皿
鍋島
江戸時代
(17世紀末~18世紀初)
口径20.2㎝
展覧会概要
戸栗美術館は昭和62年(1987)、全国でも珍しい陶磁器専門美術館として開館いたしました。伊万里焼や鍋島焼といった肥前磁器を中心に、中国や朝鮮半島の陶磁器など約7,000点に及ぶ収蔵品の礎を築き上げたのが、当館創設者 戸栗亨(とぐりとおる)です。
戸栗は、第二次世界大戦以後の日本の生活文化の著しい変化を前に、生活の道具の収集・保存を志し、次第に中でも鑑賞陶磁に惹かれ、熱心に求めました。その膨大なコレクションが初めて世に出たのが、1984年11月から1985年1月にかけて渋谷区立松濤美術館にて開催された『戸栗コレクション 有田の染付と色絵―伊万里・柿右衛門・鍋島―』でした。100点以上が出展され、「有田磁器の特色としての国際性と多様性を十分にうかがいうる」と評されたこの展覧会は、戸栗コレクション展示の原点とも呼べるものです。
今展では当時の出展品を再展示。来年に迫った開館30周年を前に、肥前磁器の名品とともに、戸栗コレクションのはじまりを振り返ります。
展示詳細
■創設者 戸栗亨と鑑賞陶磁
当館創設者 戸栗亨は大正15年(1926)、山梨県の山あいの町・南部町に生まれました。19歳で終戦を迎えた後は家業の土木建築業や農作業を手伝いながら、材木業を始めました。終戦後の生活の中、日本が復興の途を辿るのにつれ、電化製品が普及し、自転車がオートバイに、農耕機具の鋤鍬が耕運機に変わっていくさま、そして先祖伝来の民具が置き去りにされていくさまを見て、戸栗は一念発起します。
こういう時代の大きな変わり目だから、あと数年もたつと、古い民具は影も形もなくなるだろう。ぜひとも『民具館』のようなものをつくって後世に残そう――
「とにかく古い物は何でも」収集し始めた戸栗でしたが、40歳前後、昭和40年代には、信頼のおける美術商との出会いもあり、次第に陶磁器の魅力に惹かれていきます。もともと「用の美」を志向し、無名の工人により作られたという意味で古民具と通じ合うものがあったようです。中でも、興味の対象は「鑑賞陶磁」に向けられていきました。陶器の独特の暖かい風合もよく好みましたが、「焼き物は幅広く集めると、将来、やりきれなくなる」という周囲からの助言もあり、磁器、中でも中国や朝鮮、伊万里焼、鍋島焼を主眼とした収集活動に移っていきます。
当初から収集品の公開への思いは強く、収集対象の主眼が鑑賞陶磁へ移っていったことで、若き日の夢は美術館の建設へと膨らんでゆきます。「それならいい物を見せたい」と、収集品の質には強いこだわりをみせました。とくに肥前磁器は、一点一点の質はもちろんのこと、江戸時代を通観しうる内容となり、質・量ともに一大コレクションとなりました。

染付 竹虎文 捻花皿
伊万里
江戸時代(17世紀中期)
口径21.0㎝
伊万里
江戸時代(17世紀中期)
口径21.0㎝

色絵 紅葉流水文 皿
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
口径20.2cm
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
口径20.2cm
■戸栗コレクションとみる肥前磁器の研究史
江戸時代に生み出された伊万里焼や鍋島焼といった肥前産の磁器(以下、肥前磁器)は、同時代の国内においてはあくまで実用のうつわとして、生活の中で用いられたもの。肥前磁器が、現在のように美術品として「見て楽しむうつわ」、「鑑賞陶磁」として捉えられるようになったのは近代以降のことです。
近代以降の肥前磁器研究の流れを、戸栗コレクションの名品とともにご紹介いたします。
○明治時代
明治時代、古美術品といえば茶道具であり、肥前磁器はその対象としてほとんど顧みられることはありませんでした。そのような風潮の中、肥前磁器を収集したのが、来日中の外国人コレクターたちです。彼らは、型物などの古伊万里金襴手様式や古九谷様式、染付の伊万里焼、鍋島焼を買い集め、愛蔵したり、母国へ持ち帰って博物館へ寄贈したりしました。外国人コレクターの収集活動や、万国博覧会への日本の工芸品の出品などを契機に、海外で日本陶磁への関心が高まりました。
明治時代、古美術品といえば茶道具であり、肥前磁器はその対象としてほとんど顧みられることはありませんでした。そのような風潮の中、肥前磁器を収集したのが、来日中の外国人コレクターたちです。彼らは、型物などの古伊万里金襴手様式や古九谷様式、染付の伊万里焼、鍋島焼を買い集め、愛蔵したり、母国へ持ち帰って博物館へ寄贈したりしました。外国人コレクターの収集活動や、万国博覧会への日本の工芸品の出品などを契機に、海外で日本陶磁への関心が高まりました。

【型物】
色絵 荒磯文 鉢
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
色絵 荒磯文 鉢
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
○大正時代~昭和前期
大正時代に入ると、海外の影響を受け日本国内でも「鑑賞陶磁」の概念が導入されます。とくに工学者であった大河内正敏氏と、彼を中心に結成された「彩壺会」は、「茶陶」の価値観に縛られず、陶磁器を工芸品として、あるいは芸術品として鑑賞する態度を掲げ、「鑑賞陶磁」の概念の普及に多大な影響を与えました。ただし、当時、「鑑賞」の対象とされた肥前磁器は、古九谷様式や柿右衛門様式、古伊万里金襴手様式の伊万里焼、色鍋島といった色絵にとどまり、染付はほとんど取り上げられませんでした。
大正時代に入ると、海外の影響を受け日本国内でも「鑑賞陶磁」の概念が導入されます。とくに工学者であった大河内正敏氏と、彼を中心に結成された「彩壺会」は、「茶陶」の価値観に縛られず、陶磁器を工芸品として、あるいは芸術品として鑑賞する態度を掲げ、「鑑賞陶磁」の概念の普及に多大な影響を与えました。ただし、当時、「鑑賞」の対象とされた肥前磁器は、古九谷様式や柿右衛門様式、古伊万里金襴手様式の伊万里焼、色鍋島といった色絵にとどまり、染付はほとんど取り上げられませんでした。

【柿右衛門様式】
色絵 竹虎文 八角鉢
江戸時代(17世紀後半)
色絵 竹虎文 八角鉢
江戸時代(17世紀後半)
○昭和後期(第二次世界大戦後)
第二次世界大戦後は、昭和20年代に始まる「古九谷論争」や、昭和27年(1952)の大川内鍋島藩窯跡の発掘調査、昭和40年代以降増加する有田諸窯の発掘調査、初期伊万里ブームなど、肥前磁器への関心が高まり、著しく研究が進みます。とくに昭和30年代後半以降の多量の輸出向けの伊万里焼が買い戻される、いわゆる「里帰り」は、輸出向けの伊万里焼の様式展開の解明に多大な影響を与えました。「里帰り」により、古九谷様式から柿右衛門様式への移行の過程や、現在柿右衛門様式と称される一群が柿右衛門家のみならず有田内山エリアで広く焼造された伊万里焼の一様式であることがわかってきました。
第二次世界大戦後は、昭和20年代に始まる「古九谷論争」や、昭和27年(1952)の大川内鍋島藩窯跡の発掘調査、昭和40年代以降増加する有田諸窯の発掘調査、初期伊万里ブームなど、肥前磁器への関心が高まり、著しく研究が進みます。とくに昭和30年代後半以降の多量の輸出向けの伊万里焼が買い戻される、いわゆる「里帰り」は、輸出向けの伊万里焼の様式展開の解明に多大な影響を与えました。「里帰り」により、古九谷様式から柿右衛門様式への移行の過程や、現在柿右衛門様式と称される一群が柿右衛門家のみならず有田内山エリアで広く焼造された伊万里焼の一様式であることがわかってきました。

【輸出向けの伊万里焼】
色絵 牡丹梅文 栗鼠鈕蓋物
江戸時代
(17世紀末~18世紀前半)
色絵 牡丹梅文 栗鼠鈕蓋物
江戸時代
(17世紀末~18世紀前半)
戸栗コレクションを築いた戸栗亨が、本格的に肥前磁器の収集を始めたのも、第二次世界大戦後、昭和40年代のことです。そして20年ほどの間に、初期伊万里から輸出向けの柿右衛門様式や古伊万里金襴手様式、型物、鍋島焼にいたるまで幅広く収集しました。そのコレクションの初公開は『戸栗コレクション 有田の染付と色絵―伊万里・柿右衛門・鍋島―』(昭和59~60年(1984~85)、渋谷区立松濤美術館/以下『戸栗コレクション展』)においてのこと。108点が出展された同展の特長は、肥前磁器の国際性と多様性を示したことにあります。輸出向けの初期色絵、柿右衛門様式、古伊万里金襴手様式の作品によって輸出品の変遷を見せるとともに、これらの輸出向け色絵に加え、型物や鍋島焼の名品、さらには初期伊万里や輸出向け染付など、肥前磁器の多様な魅力を提示しました。とくに108点中半数近くを染付が占め、長く続いた色絵重視の風潮に対して染付も「鑑賞陶磁」とたり得ることを示した側面は、同展の意義のひとつとして挙げられるでしょう。
今展では、『戸栗コレクション展』の出展品を再展示。陶磁史の流れの中で評価され、今日まで残されてきた名品の数々をぜひご覧ください。
今展では、『戸栗コレクション展』の出展品を再展示。陶磁史の流れの中で評価され、今日まで残されてきた名品の数々をぜひご覧ください。

【初期伊万里】
染付 梅樹山水文 瓶
江戸時代(17世紀前期)
染付 梅樹山水文 瓶
江戸時代(17世紀前期)
●プレス・広報ご担当の方へ
展示予定作品の画像データ等ご用意しております。
取材は随時受け付けておりますので、下記の問い合わせ先へご連絡いただき、掲載媒体・取材内容についての企画書をお送りください。
内容を検討し、追ってご連絡いたします。
●PDFファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 『戸栗コレクション1984・1985-revival-展』プレスリリース
『戸栗コレクション1984・1985-revival-展』プレスリリース
 写真借用申請書
写真借用申請書
展示予定作品の画像データ等ご用意しております。
取材は随時受け付けておりますので、下記の問い合わせ先へご連絡いただき、掲載媒体・取材内容についての企画書をお送りください。
内容を検討し、追ってご連絡いたします。
●PDFファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 『戸栗コレクション1984・1985-revival-展』プレスリリース
『戸栗コレクション1984・1985-revival-展』プレスリリース 写真借用申請書
写真借用申請書-
【お問い合せ先】
-
財団法人 戸栗美術館
TEL:03-3465-0070
FAX:03-3467-9813
.jpg)