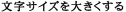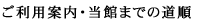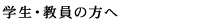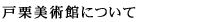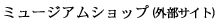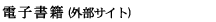鍋島焼展
会期:2016年1月7日(木)~3月21日(月・振休)

色絵 牡丹文 変形皿
鍋島
江戸時代(17世紀後半)
口径17.6×12.4㎝

色絵 壽字宝尽文
八角皿
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
口径20.8×19.4cm

青磁染付 団花文 皿
鍋島
江戸時代(18世紀前半)
口径31.0cm

青磁 桔梗口双耳瓶
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
高28.1㎝
展覧会概要
17世紀初頭、佐賀・有田に日本初の磁器である伊万里焼が誕生しました。その技術を昇華させ、17世紀中頃に創出されたのが鍋島焼。これらは、その頃輸入が困難となっていた中国陶磁器にかえて、徳川将軍家へ献上することを目的としたうつわです。佐賀鍋島藩は、技術漏洩防止のため人里離れた伊万里・大川内山(おおかわちやま)に直営窯である鍋島藩窯を築き、有田から優秀な陶工を集め、採算度外視でその製造に当たりました。
鍋島焼が技法・意匠ともに最も洗練されるのは、17世紀末から18世紀初頭。その頃の主体は、高い高台を持つ深めの木盃型(もくはいがた)と呼ばれる丸皿であり、その大きさは尺皿、七寸皿、五寸皿、小皿と規格化され、使用される色数も染付の青、色上絵の赤・緑・黄の4色に限定されていたと考えられています。描かれる文様は、献上品という性格上、吉祥・慶祝の文様が好まれたとみられ、桃、亀甲、宝尽くしなどが多く描かれています。他に絵手本帖から取材したと思われる植物や、和歌に詠われる題材も取り入れられました。これらを、丸い画面に巧みに意匠化して配置し、細部まで神経の行き届いた丁寧な賦彩を施すことで表現しています。
今展では、「色絵 十七櫂繋ぎ文 皿」を初出展。鍋島焼の色絵尺皿は現存数が少なく、本作は長くヨーロッパに伝わっていたため日本ではその存在が知られてきませんでした。色とりどりの櫂を綱で繋いだ躍動感のあるデザインが見所です。この他、最盛期の鍋島焼を中心に、その前後の作品を含めた約70点を展示し、鍋島焼の変遷をご紹介いたします。また、鍋島家伝来の図案帳の一部を特別公開いたします。
展示詳細
■鍋島焼の特徴

色絵 十七櫂繋ぎ文 皿
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀前半)
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀前半)
最盛期の鍋島焼の主体は、高い高台を持つ深めの木盃型(もくはいがた)と呼ばれる丸皿であり、その大きさは尺皿、七寸皿、五寸皿、小皿と規格化され、使用される色数も染付の青、色絵の赤・緑・黄の4色に限定されていたと考えられています。裏面に七宝結文や牡丹唐草文、高台に櫛目文を描く組み合わせが多く見られます。
■鍋島焼の変遷

色絵 桜霞文 皿
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
鍋島
江戸時代(17世紀末~18世紀初)
今展では、鍋島焼の歴史を“誕生期から最盛期まで”、 “最盛期”、 “最盛期以後”の大きく3つに区分してご紹介いたします。
≪誕生期から最盛期まで≫
17世紀後半につくられた鍋島焼には、高い高台や意匠に盛期鍋島への萌芽がうかがえますが、変形小皿が多く、丸皿の場合も見込が浅いのが特徴です。高台文様は櫛目文のほか、猪目繋文や雷文などのバリエーションがあります。また盛期鍋島には見られない銹釉あるいは紫や黒の上絵顔料、金彩の使用がみられます。
≪最盛期≫
17世紀末から18世紀初頭にかけて焼造されたもの。典型作は深い見込に高い高台のつく木盃型(もくはいがた)の丸皿で、大きさは尺・七寸・五寸・それ以下、色数も染付の青と上絵の赤・黄・緑と規格化されていたと考えられています。組皿は、丸皿であっても轆轤(ろくろ)成形後に土型を用いて調整し、墨で和紙に文様を描きそれを器面に写す仲立ちの技法を用いて下書きをしたと考えられ、同じ器形・同じ文様につくられました。
≪最盛期以後≫
18世紀以降は、享保期に出された倹約令の煽りを受け、色絵製品はほとんどつくられなくなり、青磁と染付、あるいは染付のみでも濃淡を巧みに組み合わせたものが多くなります。
18世紀後半に入ると、木盃型の丸皿のほかに、口縁が大きく外に開くものや、変形皿が登場するなど、器形の規格が崩れ始めます。また蓋付きの碗や化粧用とみられる水注など、新たな器種がつくられるようになります。
≪誕生期から最盛期まで≫
17世紀後半につくられた鍋島焼には、高い高台や意匠に盛期鍋島への萌芽がうかがえますが、変形小皿が多く、丸皿の場合も見込が浅いのが特徴です。高台文様は櫛目文のほか、猪目繋文や雷文などのバリエーションがあります。また盛期鍋島には見られない銹釉あるいは紫や黒の上絵顔料、金彩の使用がみられます。
≪最盛期≫
17世紀末から18世紀初頭にかけて焼造されたもの。典型作は深い見込に高い高台のつく木盃型(もくはいがた)の丸皿で、大きさは尺・七寸・五寸・それ以下、色数も染付の青と上絵の赤・黄・緑と規格化されていたと考えられています。組皿は、丸皿であっても轆轤(ろくろ)成形後に土型を用いて調整し、墨で和紙に文様を描きそれを器面に写す仲立ちの技法を用いて下書きをしたと考えられ、同じ器形・同じ文様につくられました。
≪最盛期以後≫
18世紀以降は、享保期に出された倹約令の煽りを受け、色絵製品はほとんどつくられなくなり、青磁と染付、あるいは染付のみでも濃淡を巧みに組み合わせたものが多くなります。
18世紀後半に入ると、木盃型の丸皿のほかに、口縁が大きく外に開くものや、変形皿が登場するなど、器形の規格が崩れ始めます。また蓋付きの碗や化粧用とみられる水注など、新たな器種がつくられるようになります。
■鍋島青磁

青磁 瓜形香炉
鍋島
江戸時代(18世紀)
鍋島
江戸時代(18世紀)
鍋島焼の名品は色絵や染付だけではありません。純白の素地に澄んだ青緑色の青磁釉を厚く、ムラなく掛けた青磁も見どころです。大川内山に藩窯を築いたのも、青磁釉の良い原料が採集できたから、とも言われるほど。器種は皿類が多く作られていますが、木盃形ではなく、変形皿が多くみられます。また、花生や香炉、置物なども少なくありません。
■図案帳
当館所蔵の図案帳は、もとは鍋島家に伝来したもので、やきものの図案や、「織物蝶図」などと記された蝶文のスケッチなどが描かれています。図案帳の役割としては、鍋島焼を製造する際の指示書、あるいは製品化した意匠の記録、藩の年寄や進物役へ提出するためのアイディアブックなどが考えられ、鍋島焼の意匠がいかにして誕生したのかを垣間見ることのできる貴重な史料と言えます。関連性のうかがえる伝世品とあわせて6点を出展予定。
●プレス・広報ご担当の方へ
展示予定作品の画像データ等ご用意しております。
取材は随時受け付けておりますので、下記の問い合わせ先へご連絡いただき、掲載媒体・取材内容についての企画書をお送りください。
内容を検討し、追ってご連絡いたします。
●PDFファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 『鍋島焼展』プレスリリース
『鍋島焼展』プレスリリース
 写真借用申請書
写真借用申請書
展示予定作品の画像データ等ご用意しております。
取材は随時受け付けておりますので、下記の問い合わせ先へご連絡いただき、掲載媒体・取材内容についての企画書をお送りください。
内容を検討し、追ってご連絡いたします。
●PDFファイルをダウンロードしてご覧いただけます。
 『鍋島焼展』プレスリリース
『鍋島焼展』プレスリリース 写真借用申請書
写真借用申請書-
【お問い合せ先】
-
財団法人 戸栗美術館
TEL:03-3465-0070
FAX:03-3467-9813
.jpg)